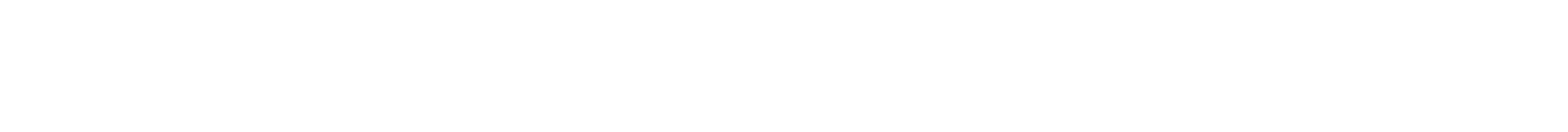今回はテニスをやる際の気持ちの切替えみたいな内容です。
例え話ですが、
自分はテニス部の部員でまだ大会出場メンバーにはなれていない。今日は試合で会場に応援に来たが試合を見ていると急に出場メンバーの先輩が怪我をしてしまい、監督から「お前、今から代わりに出ろ」と言われた。道具やウェアは借りる事になったけど、負けたら全国大会に行けない大事な試合。「そう言われても、心の準備が…」

(実際の参加規定やルールとかは置いておいて) 最後の「心の準備が…」の部分は誰でも大小、何かしらの経験がある、実感があると思います。
「今から○○を行うのだ」という自己認識、状況の理解、(勝つ・失敗しない)イメージを持つ等、自分なり準備、情況への入って行く準備をしたい
気持ちのコントロールとか難しい話ではなく、また誰に教わるでもなく、誰もが過去の経験等から
「自分が納得できるパフォーマンスを出すにはその情況に合わせた気持ちを切り替えが必要だ。気持ちの切替え無しに何となくプレイしても自分の実力は発揮できない。」
と無意識でも認識をしているからだと思います。
そんなの当たり前に聞こえるでしょうか?
でも「スポーツと気持ちの問題」は色々な場面で言われますし、具体的な知識がない中でも、スポーツをする際にそういったものも重要なんだろうなと感じる機会もあるでしょう。
“ゾーン”という言葉
プロスポーツ選手が「このポイントの時は”ゾーン”に入っていて」といった表現をする事があります。

ゾーンの定義はよく分かりませんが「ボールに集中できている」「考えなくても身体が自然と動く」とか。昔から野球で言われる表現だと「ピッチャーが投げたボールが”止まって”見える」等もそういった類かなと思います。
ただ、プロが言う”ゾーン”を起こせるようになろう、コントロールできるようにしようと取り組むのは、結果が生活に直結するような環境にあるプロ選手でもない我々には少し難しいでしょうか。
そういった状態になって発揮できるパフォーマンスの質がプロのそれとは大きな差がありますから、練習に取り組む上での”ある種の自己満足”としてはアリでも、先に『普段からできるテニスのレベルを底上げする方が遥かに効果は高い』と思うからです。
テニス初心者の方が「ゾーンがうんぬん」と言っているのをイメージすれば分かりますね。「そういうのはもっと基本が出来るようになってからね」という感じです。
因みに上達は”技術向上”より”出来ない事を減らしていく作業”から
初心者に限らず、テニススクールに通う中で “自分が出来ていない事を認識し、出来ない事を減らしていく” 作業が山のように残っています。
テニスでは自分の状態を知る事が大事です。「技術を上げる。うまくなる。」といった現状を理解しないまま現状よりも上の段階を見ている思考より「出来ていない事を減らしてミスする要因を消す」といった思考の方が”実質的な上達”を生んだりします。
スクールで上達してきた人の多くは案外自分で自分の事をうまいと思っています。
テニスに”唯一の正解”はなく、私は「あの打ち方は良いね」は言えても「あの打ち方は間違い」と断言するのは世界的権威の方でも無理だと思っています。(よく「自分は正しい。あなたは間違っている。」というやり取りがあったりします。)
自己流の打ち方が悪いとは言えませんが、人の身体の構造は多くの人が共通するというのは真理です。他の人よりうまく走れるからといって50m走を後ろ向きに走る人は居ません。ボレーを打つ、サーブを打つなどごくシンプルな”打ち方”を考えれば、皆同じような身体の使い方をする、それが効率的でミスが少ない打ち方に繋がるでしょう。
テニスにも”基本”と言われるような打ち方とその打ち方に関する説明があります。
指導ではそれをテイクバックの形、インパクトの形、フォロースルーの形と静止画のように“形”として認識させますが「どういう身体の使い方をしているからそういう打ち方になっているのか」と身体の構造や仕組みから考えると理解が断然変わってきます。形を繋げても動作にはなりませんからね。
すいません。少し脱線してしまいました。
“集中”という言葉
ボールを打ち合う際に自分としての“凡ミス”をしてしまったりすると「集中していない」と思ったりしますし、周りから「集中しろ!!」と言った指摘を受ける事があります。

ただ、この“集中”という言葉が何を指すかはかなり幅が広い気がします。
集中とは何かを一箇所に集める事でしかありませんね。
「精神を集中」する事自体より
“結果的にどういう意識や心理状態になるのか” が大事であり、それは状況によって一様ではない
という感じです。
実際「ボールに集中」すればうまく打てる訳ではありません。凝視するだけなら顔に直撃してしまいますね。
『疲労等からボーッとした状態、自分が普通だと思うプレイができていない状態』を改善しろ、何とかしろ、何をすべきか考えろ
といった事でしょうか。
この場合、
自分なりに「集中」できている状態のイメージがあるから「今は集中していない」と感じられる
訳です。
また、
普段からどういう手順を踏めば短い期間で気持ちの切替えができるのか「集中」が出来るのかを考え準備しておかないと咄嗟に出来るものではない
と思います。
自分にとってのその場面の重要度の違いも”集中度合い”に大きく関係しますね。
普段とは明らかに違うプレイができているという体験
(私のようにスクールに通って練習しているような位の人でも) 練習をしていて「今、この瞬間、普段感じる自分のテニスとは明らかに別物に感じる」という事があります。

また、事後に振り返って「あの状態に再びなるにはどうすれば良いか?」とも考えます。
それは“ゾーン”に通ずるものなのかもしれませんが、馴染みのある言い方なら “集中できている” という状態かもしれません。
普通に練習していても「今日は調子が良いな」と感じるような事はあるでしょうが、『何かしら別次元のパフォーマンスができている』という状態は何度か体感してみないと違いが分からないと思います。それ程の違いが実感できるからです。
同時に「何かしらのきっかけが無いとそういう状態にはならない」という事なのだと考えます。
練習の時のあなたは”自分の実力”を出せているか?
以前、スクールの練習に参加する際、「自分のテニスに影響を受けてしまうから、練習中、ボールを打っている時間帯は”周りの人が打っている様子”を見ない」といったことを書きました。
私はいわゆる「気にしぃ」タイプで周りに影響を受けやすい事もあるでしょうが、多くの人が「今ミスをしたのは集中できていなかったからだ」と感じる事もあり、最初に書いた心の準備の話同様、
『実際にボールを打つ、打っている時間帯では、何かしら精神状態や気持ちを切り替える』必要はある
のだろうと推測します。
もし、「俺は、レッスンの80分間、集中状態や精神状態は大して変わらないよ。いつも楽しく出来てるからね。」という方は、上で述べた『何かしら普段の自分とは別次元に感じるパフォーマンスができている』という経験が無いのかもしれません。(あるいは無意識に気持ちの上げ下げ、集中度のコントロールが高い次元で出来ているのか)
そのミスはあなたの実力を十分発揮した上で起こったのか?
言い方を変えれば、
練習をしていて、自分としては「普段やるようなよくあるミスをしたなぁ」を感じた”そのミス”は、本当にあなたの実力を発揮した結果、たまたま発生したミスなのか?
という事です。
そう言われても、ピンとこないでしょうか?
スクールにおける80分なりの練習中、ずっと相手とラリーを打ち合い続ける事はまずないですね。ボールを打っていない時間がボールを打つ時間の間に際限なく発生しています。
明確に「何分続く」とは言えなくても人の集中力が長い時間は続かないのは分かりますし、野球やサッカー、バスケットボール、バレー、そしてテニスとポイント間、プレイ間にインターバル(合間)があるスポーツであれば「プレイ中とインターバルでの気持ちの切替えをする方がプレイ中のパフォーマンスは上げやすい」 だろうという推測もできるでしょう。
簡単に「80分間、ずっと同じような気持ちで練習をしているよ」と答えられてしまうのではなく、普段の練習でも
「練習中に無数にある、インターバルからボールを打つ時間帯に入るタイミングで気持ちや精神状態の切替えを行う方が自分本来の実力、パフォーマンスが出しやすいのではないか?」
「精神状態や気持ちの切替えを短い時間でスムーズに行える手段や過程を普段から考え、自分なりに整理、準備しておく方が良いのではないか?」
と考えるようになってきました。
これも『何かしら普段の自分とは別次元に感じるパフォーマンスができている』体験が何度かあった事からです。
何かのきっかけで偶然起こり、それが何度か起こらないと実感できないですが、スクールでの練習だと、ボールを打つ事に気持ちが向いてしまい、今の自分がどういう状態かまで意識が向かないかなと思います。
各スポーツで「メリハリのあるプレイ」といった言葉がありますが、気持ちの切替えが自然と出来ている方ならボールを打つ様子がそういう風に見える気がします。
“観客モード”と”実行モード”
これらの名称は説明のため私が(悪い意味で)適当に付けています。専門用語とかではないのでご理解ください。
最初の急遽試合に出場しなくてはならなくなった例、以前書いた内容で述べた「自分のテニスに影響を受けてしまうから、練習中、ボールを打っている時間帯は “周りの人が打っている様子” を見ない」という例に通ずるものです。
スクールの練習中、自分が打つ順番を待つ際等、他の人が打っているのを見ているという時間が様々存在します。
自分はボールを打ってない、打つ準備もしていない訳なので“試合をTVで見ている観客”のような心理状態です。

ボールを打っている人達が良いプレイをしたら「ナイスショット」と自然と口から出たりします。その言葉は自分がボールを打つ事とその時の精神状態が繋がっていない部分で出ているでしょう。
順番が回ってきて自分がボールを打つ訳ですが、
「今までTVで試合を見ている心理状態で居たのに、急に “はい、ボールを打ってください” と言われてそういった心理状態になれますか?」
といった事です。

スクールでの練習でもこういった場面が沢山訪れます。
あくまで私の場合ですが、球出しで自分が打つ順番を待っている間、ダブルス練習で自分の順番を待っている間、
他の方がボールを打っている様子を見る事で『観客モード』になってしまうのを避けたい
ですし、待っている時間の中で
『実行モード』になるための準備を自分なりの手順で行っておきたい
です。
そして自分がボールを打つ準備段階に入った時に
『集中力を瞬間的に高める』ようにしたい
ですね。
私は頭で理解してからでないとうまく動けないので、これでようやく自分が意識している手順でボールが打てる、自分の打ち方でテニスができるといった感じです。
具体的にやっている事としては
『自分以外の人達がボールを打つ様子を見ない。周りの人達や飛び交うボールから視線を外して自分の真下のコート表面の一部を凝視する。逆に天井や遠くにあるものを漠然と見て凝視を解除する(遠望視)。』
と言った事です。(※)
上達したい一心で、時間とお金をかけて練習に参加している訳ですし、「なんとなく打ってミスしちゃった」では自己嫌悪に陥ってしまいます。切替えを行わないばかりに観客モードのままボールを打ってしまい、それが「自分のテニスだ。実力だ。」と思ってしまうのは勿体無い気がしています。
できるだけ『何かしら普段の自分とは別次元に感じるパフォーマンスができている』状態でボールも打ちたいです。
私は勝負の勝ち負けより良いプレイをしたいのでそう感じながらテニスできる方が“普通に”楽しいですからね。
(※) 当然、前の人が打ち終わるのを把握していないと自分の番でスムーズに流れに入れないしですし、周りで打ち合う人や飛び交うボールを把握していないと怪我の元ですからその辺りは注意しつつになります。
また、始めて練習する方はどんなボールを打つのか、どういった点が得意で苦手か把握しないと良い練習にもなりませんから、気持ちの切替えに影響のない場面 (練習中に1回休み等長い待ち時間があった際等) に観察はします。自分がどう打っているのかは分からなくても人が打っているのをみて「何故ミスするのか」を考える事は参考になりますから
“ゾーン”とかそういう仰々しいものでなくても自分の実力を出すために
我々には、世界大会の場で結果を出すための精神状態としての”ゾーン”は必要ないですね。
でも、練習の中で本来の自分の実力を発揮できるようにするためにも、プレイ中とインターバル時間の間で気持ちを切り替える、集中できていると感じられる手段や過程、手法を普段から自分なりに考える方が良いだろうと思います。
特別な事でなくて良いとはずです。
ラグビーの五郎丸歩選手で話題になった『ルーティーン』、イチロー選手も打席に入る前に決まったルーティーンを行っていましたね。(というよりベンチから出てきた所から始まって居たり、あるいは普段の食事から始まる位だそうですが。) イチロー選手が外野守備中にたびたび電光掲示板のスコアを観察していたのもホームベース方向ばかり見ている情況からの視野のリセットだと聞きました。
練習する際、コーチの球出しのボールを打つのに長いルーティーンを取るのは無理でしょうが、自分の順番が回ってきた時に合わせて、あるいは1球打って次のボールに準備する僅かな時間の中で自分の気持ちを切り替える、集中度を増すという取り組みを行う事は意味のある事だと思います。
「振り返ってみればなんとなく打ってミスしていた。」「今のは集中できていなかったなぁ」と感じられる方なら尚更からもしれません。
気持ちを切り替える工夫で直接的に”テニスがうまくなる”訳ではないでしょうが、自分の実力を発揮しやすくする、その状態で練習してこそその先の上達があるといった事はあるだろうなと思います。