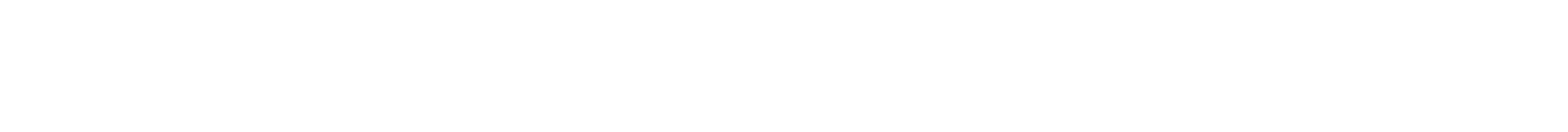ブログはテニスに関することが中心になります。
ちなみに私自身、専門家でも、競技経験者でもコーチでもない単なるリクリエーションプレイヤーです。
30代半ばで初心者からテニススクールに通い始めましたが、全然上達せず、6年半経っても初中級クラス (入門、初級の次、中級の手前) で一番下手な部類でした。他に興味が出て2~3年でスクールを止めてしまう方も多い中、「運動が苦手だから仕方がない」と週1~2回、真面目に通っていました。
ある時、契約で入っていたコーチからそれまでスクールで教っていたものと全く違う練習メニューを受け、それまで入門書や月刊誌等で読んでいた情報と実際の動作がまさにガシャン、ガシャンと音を立てて理解がはまっていく感じでした。
普及し始めていたYouTubeで海外の情報等を見ると、スクールなどで教わる「説明」に根拠が伴っていないと感じました。なぜ準備で横を向くのか。なぜジャンプするのか、なぜ下から上に振るのか。「そうするものだから」と言われ、言われる通りにやっても私には上手くできません。
2023年現在では “当たり前” になっていますが、野球やゴルフ等では、化学的根拠、計測データに基づき、運動を分析、解析する動きが出てきています。それらを見て「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、ボールに加えるエネルギー量とエネルギーが伝わる方向性がボールの質を決める」と考えましました。
我々は普遍的な物理法則の下で生活している。日常生活でもコートの上でも変わらない。誰もが慣性や反動等を使っている。トッププロも初心者も同じ法則に基づき現象を起こしているという事実が我々が頼りにすべき前提。原因・条件と結果の関係性。望む事象としてのボールの飛びや回転を得られる条件を根拠としない、確率のスポーツであるテニスをやっているのに「漠然と打っている。何となく打っている」のでは自分などまともにラリーが続かないのは当然だろうと思いました。
情報で言えば、日本では認知度のある『エッグボール』という言葉ですが、海外に『egg ball』という球種は存在しません。(egg ball像検索すれば卵の画像が出てきます) 世界的に存在しない球種を「エッグボールの打ち方はー」と説明できる方は自分で開発者したのでしょうか? 一時期よく耳にした『脱力』も英語なら『リラクゼーション』かもしれません。「リラックスした状態で打て」なら誰でも分かるし、特別な事でも無いと思います。ネットによる情報の広がりで野球でも従来からの『当たり前』がどんどん覆されていってますね。
このブログは『夏休みの課題発表』みたいなものだと思っています。某質問掲示板では「お前の考えは読む人に悪影響を与える」と出禁にさせられ、ブログも「テニスをやった事がない者の妄想」と書かれました。人に教えられる位に良く “分かっている” 方がわざわざ他のクラスまで掲示物を見に来て「こいつの言う事は嘘だ。みんな聞いちゃいけない」等と声高に言う必要はないと思います。
そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ブログで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。コメント欄を設けていないのも同様の理由です。考えを求められても、正しいとか間違いとか私には言えませんし、それを他の方と争う必要も私にはありません。ただ、自身の知識や理解を高めるのみ。それが目的で色々考え、学ばせていただいています。
最後に、例としての図や動画には3DCGソフトウェアである『MikuMikuDance』と「プログラミング生放送」のキャラクター『暮井 慧(プロ生ちゃん)』のMMD用公式データ、Vroid Studioで生成した3Dデータ、生成AIで作成した画像等をを使わせていただいています。
- 関連サイト: プログラミング生放送 – 略してプロ生
- 関連サイト: Vroid Studio
自分で撮影しないのは単純に技量不足で示したい事が示せないからです。私の場合、今、自分が出来る、出来ないは問題ではないです。また、3DCGなら正面・横・後ろ・真上から確認、撮影できる利点もあると思います。