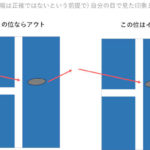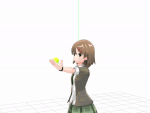テニススクールの “ありがち” 傾向
テニススクールには色々な人が居ます。年齢、性別も様々です。
私が思っているのは「テニススクールに通う際、『自分の判断、自分で通う事を決めて来ている』人が多い。「周りに行かされた」や「家族と一緒に」「友達と一緒に」という方は少ない。良くも悪くも、我が強い、負けず嫌いな人が多く、一見そう見えなくても『秘めた拘り』を持つ方が集まっている」といった事です。もちろん、テニススクールが特別ではなく、社会人の習い事等、人が集まる所は同じような部分はあるでしょう。
また、テニススクールではレベル分けがあり、基本的に自分と同等レベルの方々と一緒にレッスンを受ける事になります。1コート辺りの参加人数は10名位。
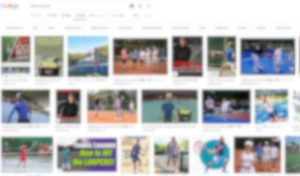
テニスを続けていると『その方なりの自信』がついてきます。その自覚はなくても始めて3ヶ月の方ですら「全くの初心者の人よりマシだ」と思うのは想像出来ますし、長く続けていれば自分のテニスに対する自己評価はそれなりに高まっていきます。

「テニスの技量・テニスの上手さ」は数値化されないです。試験で点数(絶対評価)を付けたりしません。(そういうレーティングの仕方はあるが日本では使われない)
テニススクールにおいて、自分のテニスがどの程度か判断するのは『周りと比較した上での相対評価』になり、同時にその自己評価は「あの人より強いストロークが打てる」「あの人よりサーブが上」といった判定になりがちです。
自分と同じ位のレベルの方としか練習しないし、プロみたいな人に一方的にやられる経験が度々来る訳ではないですから「その環境で通用するならOK」と安心感を覚える感じです。

週一回、毎回、同じメンバー (同等のレベル) とレッスンを受ける、練習している事でその環境で自分のテニスが通用する事が当たり前になってしまい、テニスを始めた頃の “テニスへの熱意” が収まった「周りの人達に通用している。むしろ上手い位だ。この位出来ているなら十分じゃないか」という状態に陥りやすい 気がしています。
その辺りが私自身、テニススクールを利用する際に注意したい点 だと思っています。
※同様に通い始める前の「テニススクールに通えばコーチが教えてくれる」という期待も裏切られます。10名以上を1人のコーチが担当。コーチと1対1で打ち合う時間は1レッスンで3分位とか。私は「テニススクールは整備されたコート、たくさんのボール、コーチを含めた打ち合う相手を1年を通し、朝から晩まで確保できるテニスコート利用券を買っている」と考える方がしっくりきます。「自分のテニスを上達させるのは結局自分。自分次第。コーチや周りの人達ではない」です。自分で考え、取り組んでいない。「教えてもらおう」という姿勢ではなかなか上達していきません。
誰もがプロを目指す、グランドスラム優勝、世界No.1を目指す訳ではないですから、初心者の頃と違い具体的な上達への筋道が見えづらくなる。周りに通用する現状で十分に感じてしまうのは仕方がないのかもしれません。
テニスの楽しみ方は人それぞれですから「上達より、まずテニスを楽しむ」考え方も合って然るべきだと考えます。強豪校の部活ではないので「上達を目指さないヤツは練習に来るな」みたいは考え方は論外ですかね。
テニススクールに通っている方は、自分と同じかそれ以上に費用と時間をかけて通っている。だから、自分がよい時間を過ごしたいなら、それと同等以上に周りの人に取っても自分が良い練習相手にならないといけないな」と強く思っています。そこにあるのは「相手を認める」といった事です。
「自分がやりたいテニスをやる。自分が満足するためにテニスをやる」みたいな考え方にはちょっと同意できないですが、テニススクールの特殊性みたいなものが、そういう行動を取らせやすい、そういう思考に傾いてしまう方は少なくないと思います。
そういう方の多くは、まるでバッティングセンターで良い当たりを楽しむかのように「自分が打ったらそこで終わり」で、相手のボールが飛んできてから、また「打つことを考える」みたいな感じ。相手が自分と同じテニスプレイヤーだと認識していないから、相手のテニスも観察しないし、相手自身の事も全然気にかけません。
あるとすれば「自分がボールを打った結果として相手に勝つ」といった部分だけでしょうか。
テニスをやっていると感じる『対抗心』
テニススクールに通い、レッスンを受けていると『対抗心』を感じる事があります。

前述したように「皆、それぞれに自分のテニスへの自信を持っている」状態ですし、基本的に「自分と同等レベルの人としか練習しない」です。
「参加している人達がそれぞれに拘りを持っている」環境でもあります。
結果、自分のテニスへの相対値として「周りのテニスを気にする」し、「(仮に条件付きであっても) 自分の方が上手いと思う、少なくとも同等以上だと思っているなら「負けた」事に対して悔しいと思い『対抗心』を燃やす」人達も一定数居ます。
| 変な例えですが、よく知らない他のクラスに振替 (休んだレッスンを他の枠で消化する) で参加したりすると『異世界転生した主人公が冒険者ギルドに登録に訪れると先輩冒険者が「おいおい、ここは小僧が来るところじゃないぞ。冒険者ってものがどんなものか教えてやらないとなぁ」と絡まれるが返り討ち』みたいなお決まりテンプレ感 もあったりします。(話かけず遠くから様子見しながらヘラヘラ…みたいな。私の想像がたくまし過ぎかもですが) |
ただ、この「負けた」という部分が微妙で、レッスンで行うゲーム練習の中の1ポイントだったり、ラリー練習中の1球だったり。要は、その重要度ではなく、本人が「負けた」と感じたかどうかが対抗心を抱く基準になってきます。メンドクサイですよね。
ライバル関係というのは相手の技量を認めているから成り立つ
よく「良いライバル関係は互いに切磋琢磨する関係に繋がる」みたいな話がありますが、その但し書きとして「ライバル関係とは相手の技量を認める所から始まる」のだろうと思っています。

一方的な『意地の張り合い』、相手を認めず「自分が “勝つ” 事が目的」「”勝って” 満足したい」では対抗心の押し売りでしょうか。
相手が上達を目指して練習している人ならいつまで経っても本質的な意味で敵わないのではないかと思っています。
言い方が悪いですが、文字通り「眼中にない」とかいう感じですね。
テニスの上達とは出来ない事を減らしていく作業
個人的にですが「我々レベルにおけるテニスの上達とは、出来る事を伸ばすより、出来ない事を減らしていく作業だろう」と考えています。
バックハンドが苦手だからフォアハンドストロークを多用する。参加している場で通用するなら問題ないのかもしれませんが、テニスにおいてフォアハンド側、バックハンド側のショットがそれぞれあるのは当然「必要だから」でしょう。ストロークの基本となるのが、スライス系ではなくトップスピン系ショットであるのも「そうする理由があるから」だと思います。
『テニスは確率のスポーツ』ですから、(状況等により敢えてそうする理由がないのなら) 結果に繋がる確率が “低い” 選択肢を選ぶ意味がないです。
バックハンドに苦手意識があるならフォアハンドと同じ位自信を持って打てるようにする。ローボレーに自信がない、スマッシュに自信がない、自信がないからネットプレーはしたくない (時間に余裕があるストロークしか打ちたくない)。
出来ない事を減らしていけば、出来る事が増えます。
自信を持ってバックハンドが打てるならわざわざスペースを空けてまでフォアハンドで打つ必要がなくなります。
「フォアハンドストロークに自信がある」から「良い気持ちで練習を終わりたい」からとフォアハンドばかり打っていても「出来ない事は出来ないまま」ですね。
※「出来ないなら練習しろ」「練習すれば上達する」というのは熱意みたいな部分で、自分の現状を踏まえて何をどうしていけば良いのかを具体的に考え、行動していかないと良くも悪くも変化はありません。現状維持では十分ではないから上達したいのに「手っ取り早く上達するコツを教えて」みたいな手法を取るのは逆に時間が勿体ないし、何をどうしていけば良いのか分からないままなのかなと思います。
テニススクール上級でも “全然” です。
私がテニススクールに通い始めた時、テニススクール中級でも想像が付かなすぎて自分がそこにたどり着けるのかイメージが湧きませんでした。スクール上級なんて存在すら考えられないレベル。
でも、実際の所、テニススクール上級といっても「草トーナメントで上位進出できるか怪しい位の実力?」と思っています。
試合慣れという部分も含めて1回戦を勝っても2回戦がどうかみたいな。(参加したことがないのでYouTube動画とかからの想像ですが)
つまり “全然” なのです。
そんな段階でも「自分はスクール上級。周りの人達にも全然負けてないぜ」と出来ない事を出来ないままにして「練習中の1球、1ポイントに拘り、勝手な対抗心を燃やしてくる」のは、熱意のベクトルが違うのでは? ? と思えてきます。
重ね重ねメンドクサイです。
(上級より上のレベル分けがあるテニススクールもありますが、それでも「そこまで到達できれば十分」かどうかは分かりません)
私は、練習中には精神的にも集中 (英語で言うと Concentrate ではなく Focus) したいのですが、特別親しい訳ではないのに、ポイントを取って目の前でガッツポーズしながら「良し!!」とか言われるとイラッとしてしまう 事も少なくありません。
上達に関係ない、互いに上達を目指すための練習といった雰囲気にならない『意地の張り合い』『自己満プライド』みたいな意識は邪魔に思ってしまいます。ちゃんと互いに認めた雰囲気で打ち合いをしてくれる方は大歓迎ですけどね。
相手を認め、自分を見つめていかないとずっとそのまま
テニススクールの嫌な部分みたいな話になってしまいましたが、(閉ざされた環境、同じメンバーとの練習といった意味では) 学校の部活でも似たような傾向はあるかもしれませんね。
「今、テニススクールに通っているけど、上達したいから、他のテニススクールにも通うのはどうか」といった話や「テニススクールでご一緒するあの人、外でもコートを借りて練習しているらしい」「あの人、試合とか出たりしているらしい」といった話を聞いたりします。
これらについて、個人的にはですが、
テニススクールは『自分が練習するための場』でしかなく、「通ったから上手くなる」「練習したから上手くなる」といった部分はあまり期待できない。
(だから「2つ、3つとクラスを取る。練習量を増やす」といった考え方は「練習量を増やして自分は何をどうするのか」というものが伴わないと「お金をかけて疲れるだけ」にもなる)
それでも成人がテニスを始めるのに “唯一” と言って良い選択肢はテニススクール。「整備されたコート、たくさんのボール、コーチ含む練習相手をいつでも確保する」のは個人では難しい。「テニスを教える」には「テニスが上手い」以外の経験、ノウハウが必要で「経験者のお父さんが子供にテニスを教えようとしても全然上達せず、互いに気まずくなって止める」「テニスサークルに初心者が入っても気まずくなって来なくなる」のはテニスあるある。
「他のテニススクールに通う」「他でコートを借りてテニスをやる」「試合に参加する」も「その機会で自分は何をするのか」が大事。
「たくさんテニスできて楽しい」だけが目的なら良いけど「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身。コーチや周りの人達ではない」ですから「考えてテニスをやらないと勿体ない」
という風に思っています。
誰もが上達したい訳ではないでしょうが、出来ない事を減らせば出来る事が増える、ミスが減ってテニスを続ける楽しみが増すかもしれません。
今、居る環境に慣れてしまい、周りと自分を比べて通用するから当初のような上達への熱意が収まってしまう。「緊張してもサーブを入れられる」といった “自信” ではなく、「あの人には勝てる」とった “慢心” ばかり持ってしまう。私は際限なく上達していきたいのでそういう思考が強い方は煩わしいだけですが、自分でもそういう側に偏らないように気をつけたいです。
「自分は分かっている。自分は出来ている」と思った瞬間から向上の道は閉ざされますね。ギリシャの哲学者エピクテトスの言葉に「すでに知っていると思っていることを学ぶことは不可能だ」というものがあります。ソクラテスの「無知の知」という話もありますね。
- 関連サイト:Wikipedia 無知の知
心技体とか言いますね。上達のために『ボールを打つ事』を考えるだけでなく、取り組んでいく姿勢、意識についても注意したいですね。それが望ましい結果に繋がりやすくするとも思います。