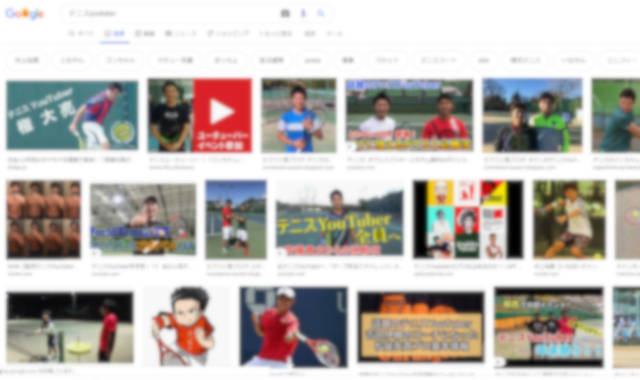テニスYouTuberという流れ
2020年現在で『テニスYouTuber』と銘打って活動されている、名乗っていなくてもそう分類されるような方はたくさんいらっしゃいます。
登録者数数十万のチャンネルからご自身の練習風景をほぼ無編集で載せておられる方まで、有名無名合わせてかなりの数になるでしょう。
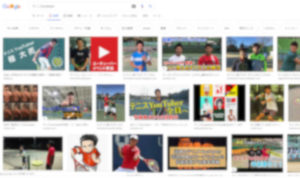
私がYouTubeを使い始めたのは日本語版が公開された前後 (2007年位) でしたが、その頃からYouTubeにレッスン動画を載せる (日本の) テニスコーチの方は居られ、それも今のテニスYouTuberの流れに繋がっていると思います。
テレビはYouTubeに “時間” を奪われた
つい少し前までYouTuberに対する一般認識は、
「常識無視でとんでもない事をやらかして再生数を得ようとする。世間一般の “常識ある大人” からは『TVで見るお笑い芸人さんの延長線上』にあるような (自分達はあんな事はしないという意味での) “侮蔑” の対象に近い」
といったものだったと思います。
その後、YouTubeを1日中見ているような子供達にとってYouTuberはヒーローとなり、「あのYouTuberは年収何億」という話が出てきます。大人達の “侮蔑” の反応は収まっていき「あわよくば自分も」という人達も増えてきました。
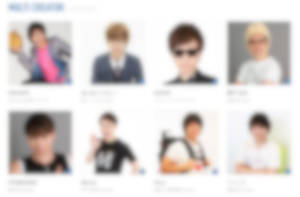
日々、感じられていると思いますが、
日本国民の一日の生活時間の一部を “占有” していたテレビが、その時間をYouTubeに奪われつつあります。
当初「子供や若い人しか見ていない」ものだったYouTubeの年齢層がどんどん上に拡大しつつあり、純粋に「TVしか見ていない」方は50代以降位の比較的年齢の高い方になるかもしれませんね。
SNSの広まりもあり、『TVが主たる情報源』な時代から『TVがいかに自分達に都合よく情報を発信しているか』が広く知られるようになりました。(今は少なくなりましたが1番組が取り上げた「〇〇が健康に良い」という話で翌日スーパーからその食材が消えるのが毎週起こっていました)
新聞社やTV局の評価がどんどん下がっていき、特定の番組、出演者への批判が目立って来てもいます。
テレビがラジオから時間を奪ったようにテレビもYouTube (を含めたネットメディア) に置き換わる流れ。数年後のテレビは現在のラジオのように「特定の対象に向けて残されているだけ」な存在になっている気がします。
2020年現在、Abema TVやNetflixのように電波を使わず『ネットだけ配信』でダメな理由がないです。
インターネット広告費の増大と出稿枠判断の厳格化
2019年、国内のインターネット広告費は2兆1048億円で初めてテレビの広告費を抜いたそうです。
ただ、YouTubeにおける収益の柱である『広告費』ですが、2018年に「登録者数1,000人以下」は対象外となり、以降も、細かい規定の更新が続く事によってチャンネル運営者が想定する広告出稿が得られにくい状況にもなってきています。
例えば
「真夏の炎天下、気温40℃の中で9時間ぶっ続けでテニスしてみた」
「有明コロシアムのセンターコートに忍び込んでテニスしてみた」
みたいな乱暴な動画に大手飲料メーカ-の広告が出てしまったら
自社のブランドイメージが傷ついてしまう
でしょう。(そういった事を認めているように思われる)

テレビの制作現場であれば「CMを流す、提供に入ってくれるスポンサーのイメージダウンになるような演出、表現を番組内では行わない」でしょうが、YouTubeの動画広告は配信者と広告出向者の繋がりが強くありません。(広告枠に割り当てられるだけ)
明確にインターネットをTV他と同等以上のメディア、媒体として扱わざるを得なくなっている、それが広告費の増大に出ている中、
「自社イメージ、自社製品に合わない動画には広告を出さない」
と考える企業(出稿側)に対し、TV他と同じような出稿側を意識した基準でコンテンツを用意する事が広告収入を求めるYouTube配信者に求められるようになってきたと思います。
「YouTubeに動画を載せて再生数を稼げばお金儲け」とはいかなくなっているのです。
広告収入や以前よりより広い世間一般からの評価を考えるなら、限りなく素人に近い方が1人で企画、出演、撮影、編集、投稿まで行うYouTubeチャンネルでもTV局の番組制作と同じ位のノウハウやセンス、戦略、リスク対策が求められるようになってきていると思います。
既に
YouTubeはTVにとって代わるメディアになっている
のですからね。
「素人だから許して」とはいきません。SNSで袋叩きにあう一般の方を日々見るでしょう。また「収益とか自分は関係ない。趣味で使うだけ」な方でも「動画がバズって100万再生」なんて事は起こります。参加者全員が収益化の方向性と “表裏一体” なのです。
YouTubeはテニスレッスンには向かない (と思う)
私がYouTubeを使い始めた頃から居る「テニスのレッスン動画を上げる」コーチや企業・組織の皆さんに、
「自分が培ってきた経験や技術、テニススクールで教えている内容を “動画で” 公開して多くの人に見てもらおう」
といった狙いがあるのは明らかだと思います。

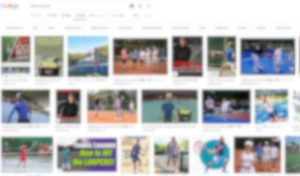
自身のコーチ業やテニススクールの宣伝のために載せる方、最近では知名度を上げサポートを受けたいプロ選手、それこそ広告収入を狙っている方も多いでしょう。
でも、個人的にですが、
「YouTube “単体” ではテニスレッスンをするのに向いてない」
と考えています。
テニスのYouTubeチャンネルを運営する。テニスYouTuberを目指す、活動される方には大事な問題と思います。
自分が(自分達が)想定していた “そもそもの部分” が揺らぎかねませんね。
いくつかその理由を挙げてみましょう。
1. 連続性に向かないインターフェース
YouTubeに動画投稿した事がある (自身のチャンネルを持っている) 方なら分かると思いますが「動画を載せたら載せっぱなし」です。
動画ですから、文字テロップが間違っても「一部修正」なんて出来ません。新しい動画を上げなおしたら、それまでの再生数がゼロに戻ってしまいます。(一部を切って短くする、他動画と繋げる等はできます。でも、理解が間違っていたらすいません)
何十、何百上げた動画がある中、「これとこれは同じシリーズだからこの順番で並べ替え」もできませんし、再生リストの機能で区分しても階層を辿って見に行くしかないし、「ただ一覧で並んで居るだけ」な表示もどうしようもありません。

YouTubeルは
動画を公開するのに都合よく作られているだけで、公開可能のオンラインストレージ (パソコンのハードディスクのようなもの) と変わらない
と言っても良いかもしれません。
Webならレイアウトや記事の並び方も簡単、目次やナビゲーション的要素も自分の意図通りに作れます。
YouTube単体ではそれが出来ない (やりづらい)。
「動画毎の連続性、繋がりを持たせて公開していくには使い勝手が悪すぎる」
と思うのです。
※アニメ全話公開を行うYouTubeチャンネル (公式) を見れば、作品Aの1~10話、作品Bの21~30話のように作品関係なくただの一覧になるのがよく分かります。
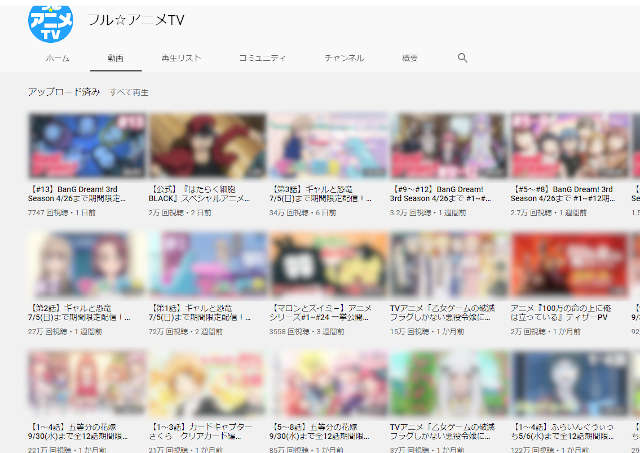
2-1. 過去動画なんて見てくれない
YouTubeで公開した動画には (許可しない設定をしなければ) コメントが付けられます。

公開した動画が好評で登録者数が増えてくると毎回見てくれる人やいわゆる “ファン” も増えてきます。「参考になった」「楽しみにしている」といったコメントは継続のモチベーションにもなりますね。
ただ、
「〇〇に悩んでいるのですがどうすれば良いですか?」
「✖✖がコツと言ってましたけどこういう場合はどうすれば良いですか?」
といった投稿者に尋ねたい質問も出てきます。
1人が質問を始めると「自分も質問しよう」としますし、1度回答してもらえると「他にも聞きたいことが」という風になります。
投稿者としては「今後も動画を見てほしい」ので出来るだけ回答していきたい所ですが、投稿が続いていけば行くほど、
『過去の動画で説明した内容』を質問されるケース
が出てきます。
チャンネル運営者からの返答で
「過去の動画で説明しましたが…」
という書き出しは日々見ますし、
「お願いだから、過去動画を見てから質問してください」
と繰り返し頼んでいる動画等も見ています。
これはYouTubeに限らずQ&Aサイトでも見られる傾向です。某Q&Aサイトのテニスカテゴリーではほぼ毎日「おすすめのラケットを教えて」という質問が登録されるのです。
自分で調べるのが手間だしやり方もよく分からない。「自分が悩んでいる」事で他に多くに方も悩んでいるとは考えない。「手っ取り早く、すぐに」解決したい。見たその場で即質問したい。
それがコメント欄のある質問対象の居る場で避けられない問題、課題になります。
回答を聞いて過去動画を見てくれる人も多少は居るでしょうが、
新しい動画が載れば「同じような質問がされる」という事が延々と続いていく
のです。
それはインターネット特有の “直帰型” 参照という問題が関係しています。
2-2. ネットではその多くが “直帰型” による参照
ブログをやっていても、各記事の直帰率 (そのページを見たら即サイトから離れる) が90%を超えるページも多いのです。

直帰率が90%というのは「そのページを見てくれた人の内、10人中9人はそのままブラウザを閉じるか、他サイトに移ってしまう。他ページも見てくる人は1人だけ」という事です。
また、参照されているページにたどり着く経緯も Google等の検索からが来ているものが9割を超えるのが実情です。(企業サイト等はまた違いますが) 基本「トップページからメニューを辿って見る」なんて行動をされる方は居ないのです。
皆さんも「Googleで検索して表示された一覧からさサイトを開く」と思います。
だから、検索結果の一覧、1ページ目 (10位以内) に入る事が大事だったりします。
直帰率、訪問経路の傾向はYouTubeも大きくは変わらないでしょう。
チャンネル登録をしている方は更新された新着動画を見てくれても、
「検索結果から訪れる。見終わったら他の動画は見ずに離れてしまう」
人達が “殆ど” だと考えないとチャンネル運営の判断に影響してしまう可能性があります。
チャンネル登録者が1,000人居てもその人達が毎回更新動画を見てくれるとは限りません。 (更新一覧に表示されても興味がなければ開かない。そもそも更新通知を見ていないかもしれない)
登録者数と再生数が比例していないチャンネルはたくさんありますね。「登録者数何万人突破記念」を喜んで良いのは人気のある、自分から身に来てくれる人達 (ファン) が大勢付いているチャンネルだけ。だからSNSで更新を知らせたり、他サイトで紹介してもらったりして “バズる (話題になってアクセスが増える)” 機会を増やす必要があったりします。
・わざわざ「過去の動画を探してみる」方はごく一部
・「同じ質問がされているかも」とか「過去の動画に説明があるかも」とか考えずその場の思い付きで「質問してしまう」
という流れは、YouTubeの組み自体からして避けられない事でしょう。
真面目で熱心な運営者に限って丁寧に対応しようとされるので尚更大変です。
「あの質問には答えたのに俺の質問には答えないのか!」みたいな方も居ますからね。
3. “ネタ” が続かない
YouTubeチャンネルを開設して、週2回の更新を目指そうと考えたとします。
週2回で月8回ですが、1年で言えば104回位動画を載せる事になります。
週1回でも年52本です。
「テニススクールで教えているようなレッスンを動画にしてあげるとして、1年で “52回” も紹介できる企画・内容を持っているのですか?」
という事です。
テニス雑誌は定期的に “ネタ” をローテーションして特集していますね。「フォアハンドストロークのコツはこれ!!」という特集をやったら半年後にまた違う解説者、違う切り口で同じような事を説明しても問題ありません。月刊誌はそういう物ですし、半年前の記事と比べて不満に思う人も居ないでしょう。
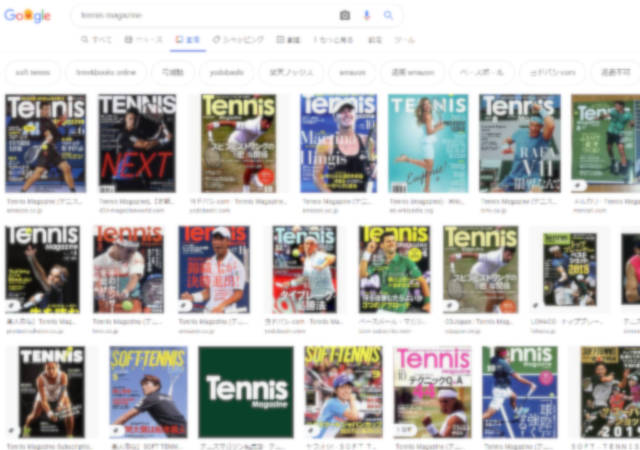
テレビのゴルフ番組は「教える事は変わらないけど3ヵ月後には違うプロで新番組に」といった事をやっています。これも1クール(3ヵ月)単位で番組が変えられるから問題ありません。

YouTubeチャンネルを “続ける限り” 続く「何を発信するか」という悩み。
動画を撮る、説明するより企画を考え方がはるかにシンドイでしょう。色々調整も必要です。
「レッスン動画をメインに…」なんて 2年、3年とは “まぁ” 続かなさそう
なのは想像が出来ます。
有名無名含めて数多くのテニススクールチャンネル、テニスコーチチャンネルが公開され、更新が止まってきたのは、この「ネタが続かない」 事がとても大きいと想像します。
4. 熱意が続かない
もう一つ、テニスレッスンで始めたYouTubeチャンネルの殆どが「更新が途絶える」結果になっている結果になる理由として熱意、モチベーションの問題があります。
広告収入や問い合わせ増、入会者増など見える形で結果が出てくるまで時間がかかるでしょうし、そもそも自分達がやっている事の効果測定自体が曖昧で難しいものです。
(企業でも言える事ですが) 実験的な企画は一部の発案者が始めるもの。その人が多忙になったり、異動になったりして「チャンネルは残っているのに更新されない」結果になりがちです。レッスン系でも続いているYouTubeチャンネルは「関係者への貢献等、提供する事自体に意義を感じている」「代表者等が広告宣伝の一環としてやっているいわゆる “肝いり”」等に限られてくる。収益だけが目的だとまず続かないだろうと思います。
他、動画で見るのは面と向かって対面しない相手、誰かにテニスを教えようとする相手ですから
「打ち方が変」とか
「下手くそ」とか
「言っている事が間違いだ」とか
その場の勢いで分別なく言ってしまう “アンチ” の声が大きく現れるのもネットではありがちです。(ノイジーマイノリティ)
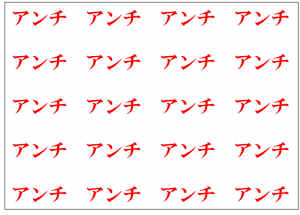
直接のコメントでなくても他サイトやSNSで酷く書かれて拡散される。反論したら「ぶちギレ」と書かれる。文字では意図が伝わらない、違って解釈される、悪意を持って歪められる。事務所が付く芸能人さんですらトラブルばかりです。
メンタルの強さや熱意は誰もが持てるものではないでしょう。
「テニスへの恩返し」といった崇高な目標で始めた投稿でも続けるのが嫌になる、続けるモチベーションが薄れてしまう事は十分考えられます。
また、他に興味を持つ事が出来た。時間もなかなか取れない。週2の目標が週1、月1回になり途絶える。「継続は力なり」と言いますが、続ける事そのもの大きな負担だと思います。
| 最近、有名YouTuberのバイリンガールChikaさんのチャンネルが “炎上” しました。ご家族と海外短期移住を続けておられましたが、新型コロナの問題で「日本に帰国します」と動画で発表した途端、「無責任だ」「移住先に留まるべきだ」と叩かれ、動画更新が途絶えています。判断については私には分かりませんが「今まで肯定的に接してきたファンの人達が急に全員敵になった (加えてこの機会に増えたやじ馬が急増)」と感じたかもしれません。YouTuberさん関連のトラブルは時々起こりますが『立ち位置としての難しさ (プロなのか我々と変わらない一般人なのか)』について何かしらの契機になる出来事だと個人的には思います。 |
「テレビを置き換える」という方向性
YouTubeはツールでしかなく、その用い方に “正解” は無いと思います。
ただ、述べてきたようなその特性を踏まえて “相性が良い” 用い方の一つが、
テレビ番組 (放送コンテンツ) の置き換え
です。
というか、動画を投稿し公開するという部分が広く認識されて広まりましたが、本来YouTubeってそういう目的で作られた気がしています。
「YouTubeは我々の生活時間の一部をテレビから奪っている」
「インターネット広告費がテレビのそれを超えた」
という事実があり、我々は「テレビを見ていた時間でYouTube動画を見るようになった」のですからね。
先週の番組内容なんて誰も覚えていない
人気のバラエティ番組があったとします。
でも、毎週見ているような人でも
先週、どんな企画、どんな内容だったか覚えている人は少ない
と思います。
その一方で、その番組の過去回を振り返える機会があった際、
「あの回は『神回』だった」
という企画がいくつも上がってくると思います。
「その企画が何年前のものかすら皆覚えていないのに」です。
(「もう5年前なのか」なんて反応はよくありますね。)
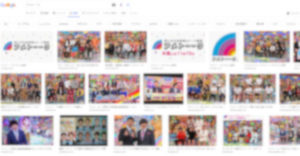
この辺りがストーリー等、持続性を想定して作られるドラマ等と違う部分です。
とは言え、ドラマでも「前回を見逃したからといって面白さが半減するような作り方はしない」ですね。毎回、印象的な場面、ストーリーの切り替えを入れてその回だけでも “見どころ” を作ります。大河ドラマ等は1年続きますし、「1回見逃したら全然つまらない」では困るでしょう。
TV番組作りと変わらない
・その動画を見る方の殆どはネットの紹介や検索結果から直接訪れ、見終わったら他の動画は見ずに離れてしまう (直帰率9割)
・チャンネル登録者ですら、過去動画はまともに見てくれない
・連続性が弱く、1回1回が独立したコンテンツ扱い
・週2本なら1年で104本「上げなければならない」
・厳密な『最終回 & 新番組』はない。2年、3年と投稿を続けていかないとならない
といった点から考えると
YouTubeチャンネル運営はTV番組作りに似ているのかもしれない
と思ってしまいます。
(今回の話で言えば、連続性が必要なドラマ等ではなく、情報番組、バラエティ系ですね)
レッスン動画として
「はーい、今日はフォアハンドストローク、全5回の内の2回目で~す!!」
なんて事を続けていても、前回の動画を遡って見てくれる人も、次回の更新を引き続き見てくれる人も”ほぼ居ない” かもしれません。
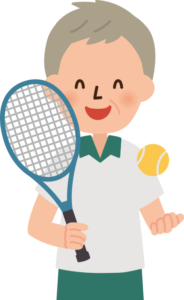
アンチの酷い声に企画を考え続けるシンドさ。
すぐに続かなくなりそうです。
トクサンTVという “パッケージ”
現在No.1 野球YouTuberと言えるのがトクサンTVさんです。
- 関連サイト:野球YouTubeチャンネル トクサンTV
チャンネル登録者数54万人、毎日1回、新規動画を投稿しており、再生数は毎回10~20万回を記録。100万回超の回もあります。
野球は全くやりませんが、自身のテニスの上達のため様々、他スポーツの情報を参考にさせてもらっています。トクサンTVさんもそういう対象のひとつです。
トクサンTVさんでは「内野ゴロの取り方」といった回があっても、複数回に渡る、連載になる事はまずありません。ゲスト出演回でも『キャッチボール編』『バッティング編』『道具や経験についてインタビュー』というように1回毎に異なる切り口になっています。
企画の内容上、以前の動画で紹介した事に振れる場合も「その動画を見なくても、その回の内容を楽しめるよう」配慮した作りになっています。(見ても見なくても良い。興味がある人だけ見れば良いというスタンス)
テレビのバラエティ番組の例で上げた
・前回がどんな企画だったかとか関係なく、常に「この1回」
・この1回だけを見て楽しんでもらえるように作る
・毎回毎回、『神回』を狙う
トクサンTVさんはテレビ番組制作的なアプローチ、パッケージ、動画作りをされている。更新動画を見ているとそんな風に思ってしまうのです。
ご存じの方も多いと思いますが、トクサンTVさんには有名TV番組のプロデューサーをやられている方が参加されています。「YouTubeチャンネルが今後どういう立ち位置になってくるか」を踏まえて初期からアドバイスされているのかもしれません。前述した「インターネット広告費がTV広告費を上回った現状、広告に対する出稿側からの判定基準がどんどん厳しくなるし、チャンネル運営側はそれに沿った方向性、動画作りをしていく責務が生じている。おかしなことをやって再生数を稼ぐというYouTuberへの認識は変わっているし、自分達も変わらなければならない」といった事を言っておられたのもこの方です。
個人的には「レッスン動画をYouTubeで見たくない」
私は「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身。コーチや周りの人達ではない」と強く思っています。
テニススクールで初心者の方が教わる内容、打ち方の説明は日本中どこでも「一言一句同じ」と言って良い位に共通化されています。テニスの入門書を開けば書いてあるような事です。
だから、日本中、どこに行っても同じように説明される内容を色んなコーチが「はい、初めまして〇〇です。これから5回に分けてフォアハンドストロークの打ち方について説明します」と “自分しか載せていない” かのようにレッスン動画を載せている事に意味を感じないのです。(「私は」ですよ)
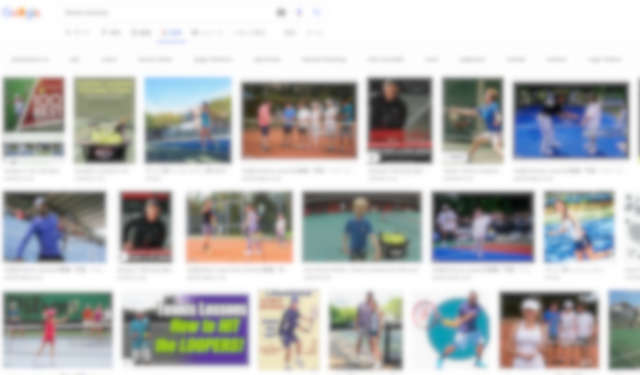
文字では伝わりにくいし、解釈が異なる場合もあり、動画で示せる、見せられるという事は大きな利点でもありますが「殆ど同じか、ちょっと違うだけのハンバーグの “基本” レシピが何百と表示される」サイト 等と同じに感じるのです。

YouTubeというツールをどう使うかに正解はない訳ですが、私は「教わる”基本とは違うけど自分で一生懸命考えた事を発信してくれる」チャンネルの方が存在意義はある (一般的な意味での “結果” には結びつかなくても) と感じます。
テニスと関係ない他スポーツや武道・格闘後等の動画が「参考になる」と思うのもその例でしょうか。
「テニスを教える」以外のアプローチ
テニスYouTuberという言葉が使われだしたのはここ数年の事だと思いますが、その在り様は従来からあったテニス系チャンネルの例が下地になっているのは間違いないでしょう。
やはり、技術や経験がある人はそれを教えたい、伝えたいと思うでしょうし、テニスYouTubeチャンネル開設の前提が『テニスレッスン』になるのは仕方ないかもしれません。
テニスをやってみた
タレントさんが自身のYouTubeチャンネルでスポーツをする、例えば、
・テニススクールに通ってみた
・コートを借りてテニスをしてみた
という動画が載る事もありますね。
この場合、タレントさんにとってテニスは動画の “ネタ” でしかなく、うまく出来る必要も、上達する必要もない。かわいいテニスウェアを着て、コーチに教わりながら素人っぽくミスする位が動画を見ている人達、ファンの人達ウケは良いかもしれません。
(あくまで想像です。ただ、この動画に「グリップはこう握った方が良い」と “上から” アドバイスするのは「企画意図を分かってない」感じ。そういう “認知” アピも含めて発信側の想定内でしょうけどね。)
複数回に分けて動画を載せても、レッスン番組ではないですから前回との繋がりを重視する必要がないです。
それこそ「基本を習った」「試合をしてみた」でも良いのです。
テレビ番組でよくある手法でしょう。
商品インプレ動画
テニスYouTubeチャンネルで見る企画に新商品インプレがありますね。
この分野はラフィノさんの独壇場という感じです。
YouTube黎明期から各メーカーの協力関係なく、自社で製品の使用感を動画で伝えてきた取り組み故の現状の評価、認識だと思います。
海外のYouTubeチャンネルでもあまり見ない (全機種紹介しない、頻度が低い等) 取り組みです。
仮に、他チャンネルがメーカーからの依頼で新商品インプレをしても見る側からは動画の作り方、表現方法、文言等含め、どうしても「ラフィノさんのマネ」と映ると思います。
実際、他チャンネルのインプレ動画を見ても、特定機種を使ってみた感想を述べるか、カタログスペックや宣伝文句をただ述べるだけ。ラケットの各部位アップを見せる訳でもない。同シリーズの全モデルと比べた感想やストリングスを変えた場合の情報等を、付け加えるなんて事はできませんね。(メーカーとしても告知は広げたいだろうけどあまり役にたたない感じ)
※でも、昔の「路地で壁打ち(みたいな事)をしてラケットの感想を述べる」頃から考えるとこの数年の「メーカーの宣伝にいいように付き合わされている」感は少し残念でもありますね。業界的に仕方がないのでしょう。
有名なYouTuberさん達が「メーカー提供の新製品を使ってみた感想を述べるだけ」の動画を日々載せていますね。メーカーとしては「低予算で数見てもらえるだけで構わない」のでしょう。その動画は『宣伝広告』であり見た人が自分で商品を調べてくれれば良い。そういう使い方だと思います。
情報を伝えるということ
テレビ番組の鉄板の企画と言われるのが、ラーメン(食べ物)ですね。(ほかに動物と子供)
予算がかからず宣伝協力も得られるのでテレビの旅番組は相変わらず多いのでしょう。
同様な理由で街ぶらロケ番組も多いです。(出演者・スタッフが少なくて済み、セット不要)
これらに共通してくるのは “情報” という部分です。
地方のテレビ局だと自社制作が地域情報番組と天気予報だけという所もあります。
例えばですが、
『全国テニスコート巡り』
というYouTubeチャンネルを作ったとしましょう。
テニスをするにはテニスコートが必要で、公営、私営問わず、皆さん、様々コートを確保しながらテニスを楽しんでいると思います。
また、普段テニスをやられない方でも「来週、友達とテニスをやる事になった」と『東京 テニスコート レンタル 1時間』等と検索される機会は少なくないと思います。
この需要の反面、テニスコートの情報は少ないですよね。
検索されるコートの情報は、街情報サイトだと古くて更新されていない事も多い。Google マップの情報も空白欄が多かったりコートの写真すら満足に確認できなかったりします。(Googleマップの情報は誰かが投稿してくれないと拡充しない)
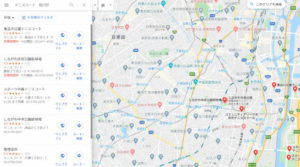
こんな中、5分ほどの動画で、
・テニスコートの様子
・設備の様子
・最寄り駅、最寄りの道路からの行き方
・予約方法と料金、申し込み先
を紹介する動画が各テニスコート毎に載っていけば、検索し参照される方は少なくないだろうと思います。
(動画毎に、ずっと検索され続けるコンテンツなので1動画辺り1万再生とか可能かも)
目的地までの行き方を紹介するタイムラプス動画がありますよね。
この手の情報を発信する際、
「まずWebサイトを作って、検索できるようにして」
といった手順を考えますが
「Googleで検索してピンポイントでその情報にアクセス、即離脱する」
のですから、(考え方次第ですが) 明確に入り口となるサイトを設ける必要がないです。
※ガソリンスタンドの価格情報を調べられるGoGo.gsさんがありますね。開始当初はWebで調べる、その後アプリ等も出ましたが、単体コンテンツでサイトを持つのは難しさがあります。よく分からず声をかけてくる企業スポンサー達に縛られたり、競争相手が色々出てきたり。
SNSで新着動画を知らせて広めてもらう位で良いと思います。
現時点で「競合が居ない」のですからやりやすさはあるでしょう。
勝手に載せると個々に問題になりかねず、テニスコート側の許可を取る必要もあるでしょうから、
「テニスコート レンタル 東京」
と近い所から始めて
「テニスコート レンタル 神奈川」
と広めていけば良いと思います。
遠距離であれば、コート運営者か協力者に動画のフォーマットを見せ「同じような動画を長めに撮ってきてくれればこちらで編集するから」と言えば地域も広げられるでしょう。
Googleマップを使って現地に行かなくてもその経路や場所が正しいか確認可能です。
コートが閉鎖になったり、リニューアルしたりしたら作り直して古い動画を削除していけば更新の手間もありません。
動画広告も期待できますが、コート側や関係者のスポンサードを得る方向性もあるかもしれません。(それで儲けるというより労力の対価をいただく程度?)
まぁ、思い付きですが、YouTubeの特性を生かしたコンテンツ作り、且つニーズもありそうな内容かなと思いました。
「テニスを見せる」「テニスを教える」で良いのか?
テニスYouTuberという括りに限らず、テニス系のYouTubeチャンネルであれば
「テニスを教える」
「テニスを見せる」
といった辺りから考える、始まる事が多いと思います。
有名選手など、そういった発信が求められている方もある程度は居るでしょう。
同時に圧倒的な競合の中で注目されない、いつしか埋もれてしまうチャンネルの方が圧倒的に多いと思います。
「他チャンネルの事はよく分からないし、知っている所もそれでやっているからとりあえずそれでやってみようと思う」
でも良いですが、
それらのチャンネルと競合、上回らる戦略、計画を持たないまま1年後、2年後に続けられているか
を考えてみてはどうかと思います。
※もちろん、全ての方が広告収入やアクセス数を目指している訳ではありません。投稿するのが目的といった方も居られます。
述べてきたように、私は
「テニスレッスンのような動画はYouTube単体での運用には向かない」
と考えています。
単発、1回の動画ならともかく、チャンネルとして続けていけば行くほど、見る人が増えるほど、悩みも増えてきます。
過去動画は見てくれない、同じ質問があるか探してくれない、説明で意図した通りに理解してくれず間違った解釈を前提に質問してくるといった事が続きます。「下手くそ」コメントする、SNSで悪意を拡散するアンチも発生します。
・競合も多く、独自性が出しづらい。埋もれてしまう。
・「チャンネル登録者を増やす」以外に明確な戦略もない。
・続ける中でネタも無くなってくる。多忙もあり更新できない。熱意も薄れる。
のであれば、自身の経験や技量があっても「テニスを見せる」「テニスを教える」に拘らず、
テレビ番組の置き換え、テレビを見る時間の代わりに見てもらうコンテンツとして「1回1回で完結するパッケージ」「その1回となる神回を作る」事を目的に動画を作る、発信するチャンネルがあっても良い
と思います。
環境はあるのですから、そういう企画者、発信者、プロデューサー的発想の方がどんどん出てきて良いと思います。
野球YouTuberであるトクサンTVさんの例。「野球を教える」系のチャンネルと比較すればその違い、分かりやすい効果の違いは明らかでしょう。
タレントさんの「テニスをやってみた」動画の例のようにテニスが上手い必要もないです。(「テニスを見せる」「テニスを教える」系だとどんな選手、コーチでも「下手くそ」とか言われます。「自分でやってみせろ」と “ぶちギレ” てもネタにされるだけです)
どこまでがテニスYouTuberなのか線引きする意味はない (教えないとダメとか、試合や練習を見せないとダメとか、経験から名言を言わないとダメとかない) かなぁと思います。
テニスが好きだからちゃんとやってくれない、テニスを軽んじる感じは嫌ですけどね。
2020.06.25 追記: 「教えてやる」系は再生数が伸びていない
このブログを書いた後もテニスYouTubeチャンネルの流れを見ていますが、やはり、
配信側の態度や口調関係なく「教えてやる」という感じのテニスYouTubeチャンネル、YouTube動画は再生数が伸びていない
ですね。(印象ではなく数字に出ている)
4年ぶりに投稿を再開された『レッスン系』のテニスYouTubeチャンネルさんが当時の10万再生から「毎日投稿しているが再生数は全て100回位」なのは時代の流れなのでしょう。
昔はそういう動画しかなかったし、皆もそれを求めていたけど、今は『観る側に近い立ち位置、視点』な配信者が主流になっています。ネットの “双方向性” もあるでしょう。見る側が一方的に「先生!!」と崇めたてる時代じゃないですし。
『実績のある有名野球選手』の説明なら純粋な “興味” から見てくれるでしょうが、全く同じ事を言っていてもその辺の指導者の方だと難しいでしょう。(そもそも動画の存在までたどり着かない)
「2018年位から既存のテニスYouTuberさん達の動画再生数が下がってきていた」のが疑問だったのですが、少し分かった気がしています。
- 利用者の幅が広がり、YouTube動画に求めれるものが変化した。
- 世間一般のYouTubeへの認識、接し方が変わってきた。
- その結果、テニス動画に求められるものも変わってきた。
- 「情報を探して動画を見る」だけではなく、見ていて楽しい、継続して見られるようなエンターテイメント性が前提になってきている。(TV番組に近い)
- テニススクールのレッスンを動画で上げてもネット利用者の興味を引く事は難しくなっている。(「そういうのは “もう” 良いから」)
- 「説明した動画内容に対して質問を受け付けます」という手法も “良い手” とは言えない。(ライブ配信、或いはSNS向きの手法)
といった事なのかもしれません。