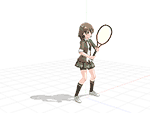AgStyle TennisさんのYouTubeチャンネル
AgStyle Tennisさんは2013から学生テニスの試合動画を上げ続けられておられるYouTubeチャンネルです。
以前は画質や撮影アングル等、テニスの試合動画としては見づらく感じる事 (室内や照明下は難しそう) もありましたが、撮影機器の進化や経験値等もあるのでしょう。最近の動画はどれを見てもとても見やすくなっています。
また、学生テニスの試合動画を継続的に見られる貴重なチャンネルであり、開催される大会内ですが、ほぼ毎日、複数の動画を投稿されている熱意に感服します。
最近見て興味深かった試合動画
私はやってもダブルスのみ、シングルスの試合はほぼやらないので、学生テニスの試合動画も見るのは上位選手同士のダブルス位になります。やっぱりトッププロに比べればミスで入るポイントが多いしテンポも遅くなる。比べる訳ではなく『見て楽しむ試合』ならプロの方を見るという素人考えです。
ただ、タイトルや選手名を見て興味を引いた動画はシングルスでも見るようにはしており、最近、興味深く見させていただいた試合動画がひとつあります。
#スーパールーキー【2019王座/SF/S1】阿部宏美(筑波大) vs 藤原夕貴(姫大) 2019年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 準決勝
2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合の女子準決勝、筑波大学対姫路大学でのシングルスです。タイトルを見れば「ずばぬけた実力を持つ選手が(おそらくどちらか1人)出ているのだろう」と感じますね。
結果から言えば筑波大学1年生の阿部宏美さんが6-1、6-1でほぼ一方的という感じで勝利します。
詳しくないですが対戦相手の姫路大学が (大学生の標準的なレベルで) 弱いという事もないのでしょう。日本一を決めるトーナメントの準決勝まで来ている大学ですし、対戦相手の藤原夕貴さんは4年生です。筑波大学は実際に強くこの大会では優勝していますが準決勝、決勝の全試合を見てもここまで一方的なスコアはありません。(因みに阿部宏美さんはトーナメントで単複6試合に出場していますがここまでの点差ではなくてもその全てで勝利しています)
阿部宏美さんについて
阿部宏美さんについてちょっと検索しただけでもものすごい経歴が出てきます。


全日本ジュニア選抜室内優勝、インターハイ優勝、浜松ウイメンズオープン (ITF) ベスト4といった具合です。過去成績を少し見た限りでも中学生の頃から強豪選手だったみたいですね。
対戦相手とのテニスの違い
AgStyle Tennisさんの動画等で拝見したりしている位ですが、対戦相手は『女子大学生選手としてはよく見かけるテニス』だと思います。
一生懸命打ってもサーブの速度はあまり速くなく、ラリーを繋いで相手と打ち合う中で1発機会を作って相手に無理な返球をさせてポイントを奪うとかそんな感じです。
圧勝する阿部宏美さんのテニスは女子プロ選手でも上位に見られるような内容に見えます。
素人目に見ても以下のような違いを感じます。
・打つ打点を落とさない
・相手に時間を作らせない
・浅いボールは常に前に出て攻撃する意識
試合前から相手の経歴や強さは知っているのでしょう。対戦相手の選手が諦めにも似た表情で淡々と試合を進める (進めざるを得ない) 様子が印象に残ります。
打点を落とさない
女子大学生の試合でもあり物凄く速い速度で打ち合い続けるというシーンは多くありません。相手のボールに対して十分下がって待ってから打てば自分の準備時間が取れ楽な反面、そのボールを打った相手にも『打って返球されるまで』により時間を与えます。そこから相手に厳しいボールを打つとなると速い速度、強い角度等が必要となり、ミスの確率も増します。相手も心理的にも身体的にも準備して待っていますから (追いつかれたら) 厳しく帰ってくる可能性もありますね。
男子プロのように速いボールをハーフバウンドで打つ訳ではないですが、打点を落とさない。1歩中に入って打つだけで相手は「(普段打ち合う相手より) テンポが速い。構えて準備する時間がない」と感じると思います。中に入って打てれば角度もつけやすく、相手の時間を奪っているので速度も厳しいコースも不要で「相手は追いつけない」結果に繋がるのでしょう。
以下は最近T-PRESSさんのYouTubeチャンネルに載っている全日本テニス選手権ダブルス優勝の佐藤博康プロが全日本出場のための指導を行うという動画です。
テニス 全日本を狙う本気の指導 時間を奪う攻撃 そのポイントは?
佐藤プロと相手選手のチャンスやタイミングに対する感覚の差というのは動画だと良く分かる気がします。「状況判断し、居るべき場所に居て、その際に準備も出来ている」といった事が身についていないと準備が出来ていない状況、残された時間で間に合わせるようよう無理のある動きになる気がします。(実際に指導を受けていると「やるので精一杯」になるのでしょうね…。佐藤プロ相手に緊張もしそう)
相手に時間を作らせない
テニスのプレイというのは色んな要素が組み合わせさって成り立っていると思うので “ある一要素だけ” を切り出して「それだけをやれ」と言うのは適当でないです。先の「打点を落とさない」で書いた事とこの「相手の時間を作らせない」が重なっているのは分かりますね。
動画でも出てきますが、女子大学生の選手を見ていると「ロブ気味に打って時間を作る」という選択が多くありますね。

もちろん「戦略的にロブを使う機会」も多いのでしょうが、私は
「相手の攻撃テンポを反らす。タイミングやリズムを一旦 “均等” に戻す。ラリーの打ち合いで厳しい状況で打つ場面ではないが “時間を作る” 事で自分も心理的に落ち着きたい」
といった
(戦略的な意図を持ってではないという意味で) なんとなく使ってしまう
事も多いのかなと思っています。
(厳しく打たれた際の返球としてのロブは「返すので精一杯。とにかく上げて時間を作る。深く攻撃しづらい所に入ればラッキー。」という感じですね)
こういったロブを打たれた場合、相手は普通に”待って” ストロークで返球するか、かなり下がって同じように高い軌道で返球するかといった場面が多いかなと思うのですが、阿部宏美さんは逆に前に出てハーフバウンド気味に返球したりしています。(少なくとも相手のショット選択に “お付き合い” しない)
相手選手がベースライン後方で待って (選手によってはバウンドするボールを頭よりも上の力の入りづらい所で) 返球してくるのが自分にとっての”普通の対応” なら、
「自分が打ってボールが帰ってくるまでの時間がはるかに短くなる、気持ちの準備間に合わないし、どういう返球が来るのかも想像が付かない」
となるのが想像できます。
バウンドに対する場所取りやタイミング、打ち方に “慣れ” は必要でしょうが、緩いボールは待って強く打とうとするよりバウンド直後に軽く面を合わせて捉える方が楽だったりしますね。
ボールを飛ばすエネルギーは
1) 重量と速度を持って飛んでくるボールのエネルギーをラケット面で反発させる
2) 重量と速度を持って前進させるラケットのエネルギーをボールに伝える
の2つと考えられます。
ネットに近い位置で飛ばす距離が比較的短い、準備時間が取れないボレーは相手ボールのエネルギーを反発させる事に重きを置いたショット

自ら上げたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは自分でラケットを加速させ、ラケットの持つエネルギーで飛ばすショット

ネットまでの距離、飛ばす速度、コース、回転量、ショットの違い等、状況に応じて選択を行うストロークはボールの持つエネルギーと自らラケットで加えるエネルギーのバランスを取るショット

という感じです。
こう考えれば、相手が打つ時速200km/hのサーブをストローク同様の「大きなスイングで打ち負けまいとする」のがいかに目的に合っていないかが分かります。
(「ボレーはこうやって打ちます」「リターンはこうやって打ちます」といった『ボールの打ち方』を教わる中ではこれらは説明されないでしょう。自分で認識して状況毎にどうすべきか考えたいです。)
自ら「相手のロブに対してしっかり後方に下がり、待ってから打つ」という選択を選ぶ事自体はアリでしょうが
試合全般を通して自分の方が優位に立ち、試合を自分が思うように進める。実力差以上に相手に「自分のテニスをさせてもらない。何をやってもやられてしまう。」という意識を持たせるには相手に考える、工夫させる時間的、心理的余裕と与えない
のが効果的だと思います。
そして「時間的、心理的余裕を与えない」ために、
打つボールの速度が速くなくても、ネットまでより近い位置で打つ、飛んでくるボールを (当たり前に) 待って打たないだけで「自分が打ってから相手の返球が帰ってくるまでの時間が短い」と相手に感じさせられる
のは想像が付きますね。
強い速いボールを打ち続けるという事でも同じような事ができますが、当然、自分の負担やミスも少なくなります。
道具の進化により打ち合うボール速度、ボールの威力は上がりましたが、速度の向上には物理的限界があります。(時速260km/hのサーブは打てない) テニスの進化が「相手の時間を奪う方向に向かっている」のは当然の流れです。意識を変えるだけで我々でもすぐ取り入れられる、強いボールを打つより確率が高く無理がないなら考えてみるべきでしょう。
浅いボールは常に前に出て攻撃する意識
先に上げた2つ同様、全ては繋がっている訳ですが
「相手の浅いボールに対して常に前に出る準備が出来ている」
「こういう状況ではこういうパターンで確実に決める」
という選択肢が普段の練習から身についているといった事だと思います。
2014年にフェデラー選手がPROSTAFF97を使い “復活” した際、「誰も見向きもしなくなったネットプレイを復活させ成功した」とか言われました。
確かに2014年シーズンは不自然なほどネットプレイを多用し、2015年にはスニークインによるリターン『SABR』を見せたりしましたが、フェデラー選手のこの姿勢が示したは、
「よりネットに近い位置で攻撃した方が得点確率は高くなる」
というテニスの “常識” を再定義したものといった感想を持ちます。
ベースライン後方から強いボールを延々打ち合うラリーは試合時間を長くし、選手の負担を高めます。
従来のサーブアンドボレーが「自分がネットに付いた所から相手とのやり取りが始まる」のに対し、フェデラー選手が示したのは
「ネット近くでポイントを取れる状況を自ら意図を持って作り出す。そうすれば (相手がネットプレイに慣れていないという点も含め) 1発で決められる事も多い」
といった事だと考えます。
ボレーに定評があり、年齢的に試合時間を長く取りたくないであろうフェデラー選手なりの方向性でしょうし、自らの望む試合運びをする、相手を自分の土俵に上げる、相手の時間を奪う、気持ちよくラリーをさせない等、現代テニスの方向性にも合っているのだろうと思います。
フェデラー選手はベースラインから下がらない。ハーフバンドで打ったりもするのが特徴ですが、こういった変化を見るに、よく言われる「ベースラインから中に入って打つ方が攻撃的 (当然飛ばす距離も短くなり、高い打点でも打ちやすいから回転を減らせたりする)」よりテニス的に何歩も先に進んでいるのだろうと思っています。
実際、フェデラー選手が切り開いた新しいテニスの進化に対し、ここ数年で、シャポバロフ選手、ティーム選手、チチパス選手、そしてナダル選手辺りが『ネットで確実に決められる状況作り』を常に意識している印象を受けています。(素人考えですが)
Daniil Medvedev vs Rafael Nadal | US Open 2019 Finals Highlights
女子学生選手対ツアー選手の対戦という感じ
私は選手やツアーに詳しい訳ではなく、阿部宏美さんが日本人選手としてどの位の位置 (ランキングではなく) に居られるのか分からないのですが、試合を動画で拝見するに「女子学生選手対ツアーを回っている選手の対戦」といった違いに感じます。
ありがちに「選手のレベルが違う」と言ってしまうのではなく、
やっているテニス自体が違っている、何世代も違う次元のテニスで対戦している
といった印象を受けるものです。
例が良いか分かりませんが、木製ラケット時代の選手が現在のカーボンラケット&ポリガットの “一般的な” 選手と対戦しただけでも「ボールが速くて全然勝負にならない」と感じるだろう事は想像がつきますね。
私は普段からテニススクールのカーペットコートで、オムニやクレー等の遅いコート、或いは弾むハードコート等でテニスをする機会が殆どないのですが、以下のともやんテニスチャンネルさんの動画でも言われているように「ボールが速くなるからとポジションを下げる方が居るが逆に前に入る。下がるとボレーされ放題になる」のは実感します。
ともやんが学生時代のペアと草トー出てみた!前編【テニス】
カーペットコートの影響なのか、ハーフバンドでボールを打ったり、ベースラインよりかなり中に入ってリターンを打ったりする (どんな速度で飛んでくるか分からない相手のサーブを不確定な時間 “待って” 打つのが辛い) のは苦にならなくなりました。
個人的に、テニス選手としての人間性等でナダル選手が好きですが、プレイを動画で見るのはフェデラー選手が中心にはなってしまいますね。
Roger Federer Claims 10th Basel Title | Basel 2019 Final Highlights
リズムよく速いタイミングのテニス、相手が速いボールを打っても受け身にならずに主体的に対応できるテニス、予測、ボールへの接近の仕方、打点への入り方、打つコース、相手にどういう対応をさせるべきか等々、技術云々ではなく、テニス自体が私のようなものでも参考になる感じです。
今回取り上げさせていただいた試合動画を拝見して改めて自分がやりたい、やるべきかなと思うテニスの方向性を再確認した感じがしました。
コーチの球出しのボールを “飛んでくるのを待って” 打つ。常にベースラインの辺りに構え、短いボールは追いかけながら打つか諦めて追えない、深い弾むボールは下がれず頭の上で無理やり打とうとする。最初の頃の打ち合う速度が遅い段階ならなんとかなっても相手の打つ平均速度が上がる、カーペットのように速いコートでテニスをするなら自分の実力以前に「うまく打てない機会ばかり」になっていくだろうなと思います。
自分が打つボールの威力が上がるという事は “同じレベルに居る練習相手のボールも同様” という事で自分が打つ事ばかり考えていても相手ありきのテニスでは結果に繋がりませんね。
相手がその事を考え始めた途端「強いボールを打って相手を打ち負かして満足」とばかりにはいきませんからね。